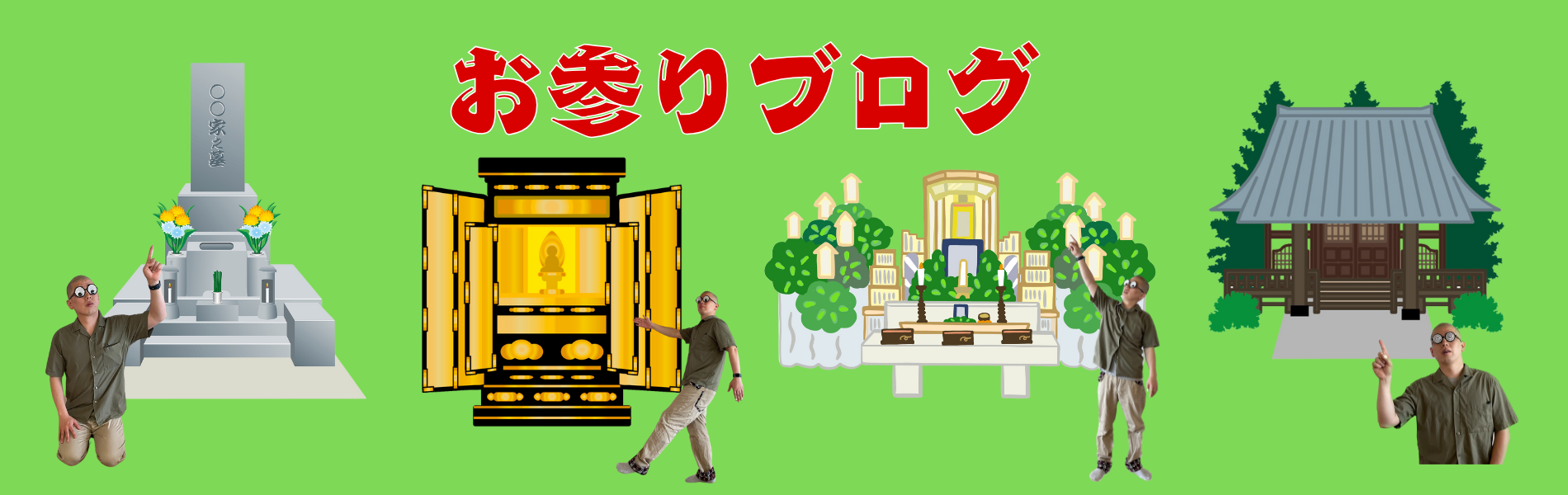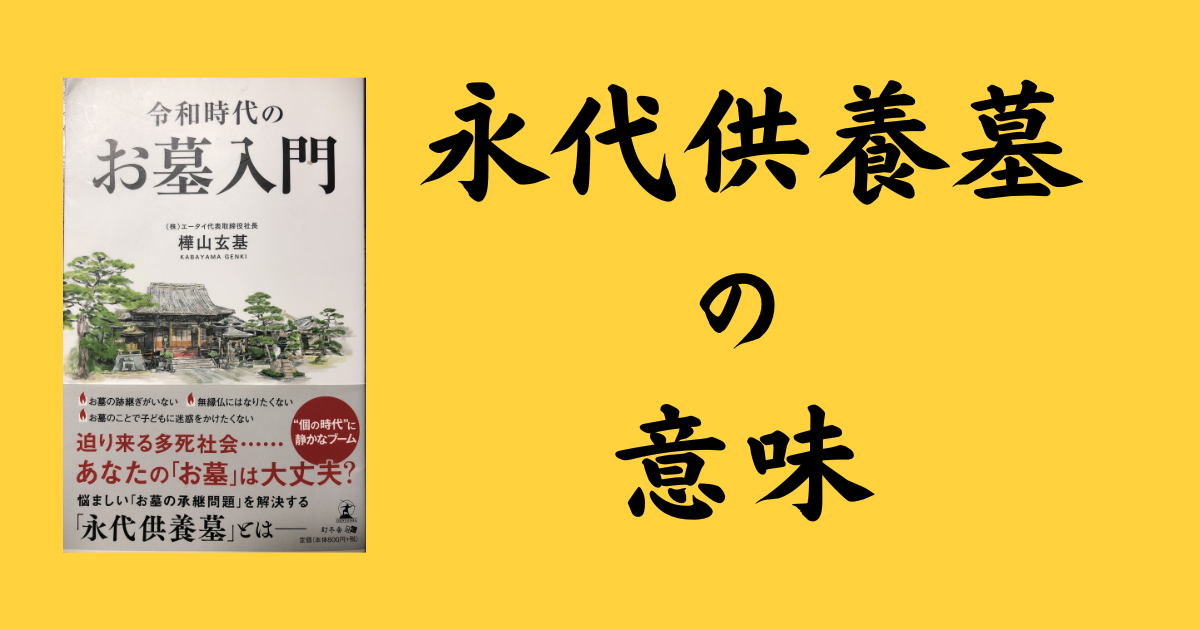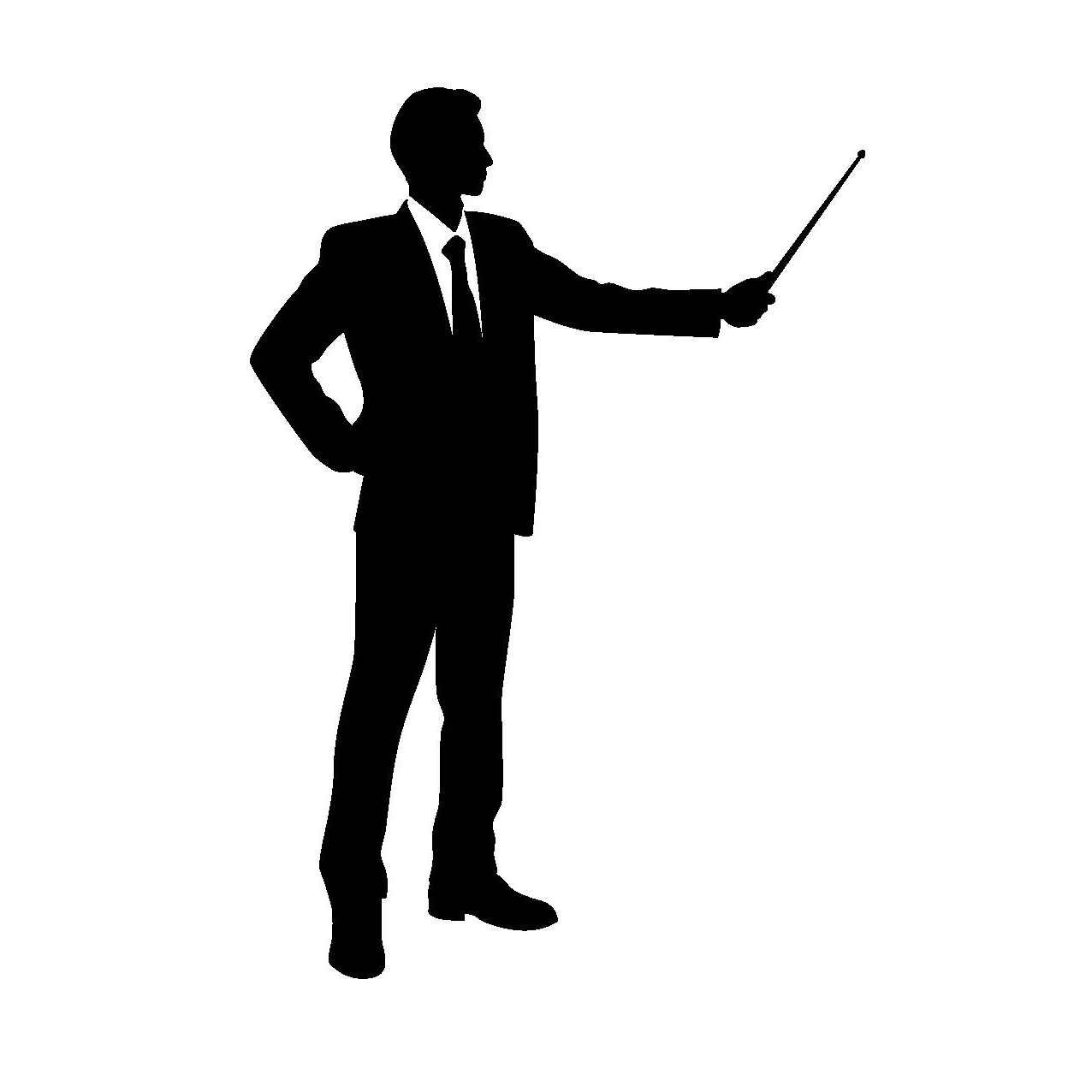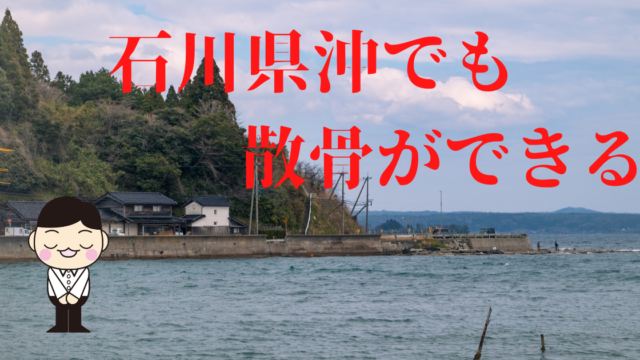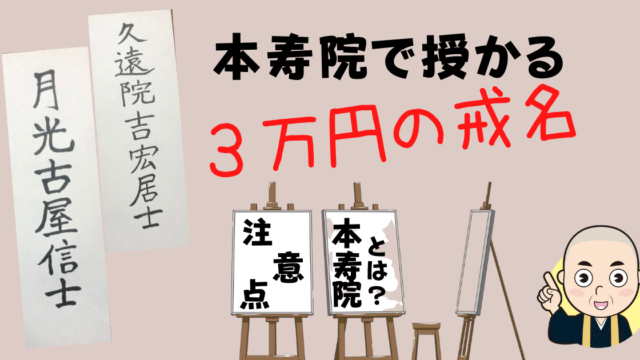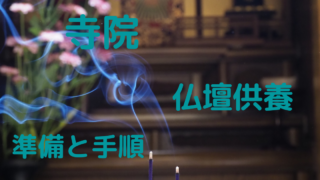亡くなった後、皆さんのお骨はどこで供養されるでしょうか。
多くの方は、先祖代々の墓地かもしれません。
しかし今、都会を中心にその流れは確実に変わってきています。
そして随分前からですが、「永代供養墓」というお墓が人気を博しています。
今回は、樺山玄基氏の著書である『令和時代のお墓入門』を参考にさせていただきながら、解説していきます。
樺山氏は、2004年に設立された株式会社エータイの代表取締役社長を勤められている方です。永代供養墓が認知されていない頃から事業を展開しておられ、年間2万件近いお墓の相談を受ける永代供養墓のパイオニア的存在として活動されています。
永代供養墓の種類、そしてその金額は様々ありますし、色々なところで紹介されていますので、この記事では永代供養墓の意味について重点的に書きました。
永代供養墓の名前は広まっていますが、契約をされる方は事前にその意味についてもしっかり理解しておきましょう。
お寺で勤められている永代経

永代供養という概念はこれまでもありました。
例えば、石川県のお寺ではよく「〇月〇日 永代経執行」の張り紙が見かけられます。石川県でなくとも、皆さんの近くのお寺でも勤められているのではないでしょうか。
永代経とは、お寺に納骨をしてある故人の供養です。一年に一回、決まった時期に勤められます。
そこには、故人の遺族の方がお参りに来ることが多いですが、お寺で供養を引き受けるというのが永代供養ですので、遺族がお参りに来られなくても勤められます。
お墓であれば、昨今よく言われている家族状況の変化などでお参りが出来なくなる可能性もあります。お寺では、毎年必ず供養のお経が勤まるから安心して故人を預けることが出来る。
それが永代供養です。
お寺では永代経のような行事の他にも、毎朝お勤めがありますので、常にお経が勤まっている場所という安心感もありますね。
本書でも樺山さんは、永代供養墓を通じてお寺さんとのご縁が出来て、お寺が今一度、心の拠り所としての存在になるよう願われています。
永代供養墓のイメージの変化
無縁墓ではない

本書では、この永代供養墓は元々無縁墓をオブラートに包んだ言い方とされていたこともあったと書かれています。
皆さんの近くの墓地を見てみますと、もしかしたら隅の方に永代供養墓と書かれたお墓があるかもしれません。そこには、跡継ぎの途絶えたお墓にあったお骨や引き取り手のなかったお骨が納骨されているのではないでしょうか。
それらのお骨は一般的に無縁仏(むえんぼとけ)と言われます。
永代供養墓とは元々は、そのような遺骨の引受先として墓地に一つ存在しているものという理解がありました。だから、筆者の所にも、「永代供養墓に親は入れません」と否定的な方もいたようです。
しかし永代供養墓であるならば、無縁墓ではありません。管理するお寺や団体が供養をしてくれるお墓です。むしろ自分がお参りできなくなっても、無縁墓にならないように永代供養墓に納骨をするのですね。
納骨堂のイメージへ

皆さんは永代供養墓というと、上記に紹介したような墓地を想像するでしょうか?
最近はこの永代供養墓というと、室内の個別の小さな部屋にお骨を納めるタイプを想像する人も多いでしょう。
特に都市部では場所が不足していることや、納骨堂アクセスの良さから納骨堂を選ばれる人は増えています。
しかし本書には「永代供養墓は屋外が原則」ということが紹介されています。
納骨堂にお骨をおさめることは、法律上、埋葬とはいいません。ドライな表現になってしまいますが、「一時預かり」の位置付けなのです。つまりいずれは、その場所を移動し、どこかに埋葬することを前提とし、期限付きで保管されている場所なのです。 『令和時代のお墓入門』P120
このことは永代供養のデメリットとしてよく書かれます。
永代供養といっても多くの場所では33回忌を期限として、納骨堂ではなく外にあるお墓に移されます。収めた納骨堂に永遠に入っているわけではないということです。
もちろん、契約する時にその旨は書かれていますし、納得の上で納骨をします。また、場所を移してもお寺さんが供養してくれることには変わりありません。
だたし、個別の部屋ではありません。多くの場合は33回忌をもって合祀されます。
仏教では33回忌をもって弔い上げとされますので、人によってはデメリットとは思わないのでしょう。

埋葬をしない以上、永代供養墓とは言わないようですが、今現状はそういう認識ではないのでしょう。納骨堂っであろうと、後に合祀されようとお寺さんが先の供養を担ってくれることが永代供養です。
形にも人間関係にもとらわれない、永代供養墓

永代供養墓はこれまでのお墓に比べ自由度が非常に高く、ガラス素材のものを使ったお墓もあると本書でも紹介されていました。骨壺が見えることで「故人を近くに感じられる」と好評のようです。
最近は樹木葬という樹木の下にお骨を埋めるものも人気が出てきていますし、その樹木葬にも永代供養はついています。トウモロコシの繊維で出来た骨壺で土に還るというものもあるそうです。
そして人間関係にもとらわれません。
本書の最後には、実際に永代供養墓を設けているお寺さんのお話が掲載されていますが、申し込まれる方の関係性も様々です。
独り身など承継者がいない方の申し込みはもちろんですが、「生涯の友人と一緒に」や「籍は入れてないけど夫婦同然」という方もおられるようです。このような柔軟性は従来のお墓にはないものです。
決してこれまでの伝わってきた先祖代々の墓が悪いわけではありません。むしろ石川県ではまだ多くの方が従来のお墓にお参りをしています。家族の形態は地方であればまだ強い結びつきがあるからです。
本書の「おわりに」の部分で筆者は、
「家のお墓に入る、という考え方から、自分のお墓を持つ、という考え方に変わってきているのです。どんなお墓で、どこにあって、誰と一緒に入るか、それらをかなり自由に選択できることが、家にとらわれない個を重視した今の時代に合っていると自負しています。」 『令和時代のお墓入門』P170~171
と書かれています。
おそらく今はまだ石川県では、「個」より「家」が重視されているのでしょう。
しかし、石川県でも散骨や樹木葬の広がりは見られます。世代が変わればガラリと変わるのが葬送儀礼です。いつか私の周りでも、これまでの先祖代々のお墓ではなく、永代供養墓に納骨する人の方が多くなる日が来るのでしょうか。