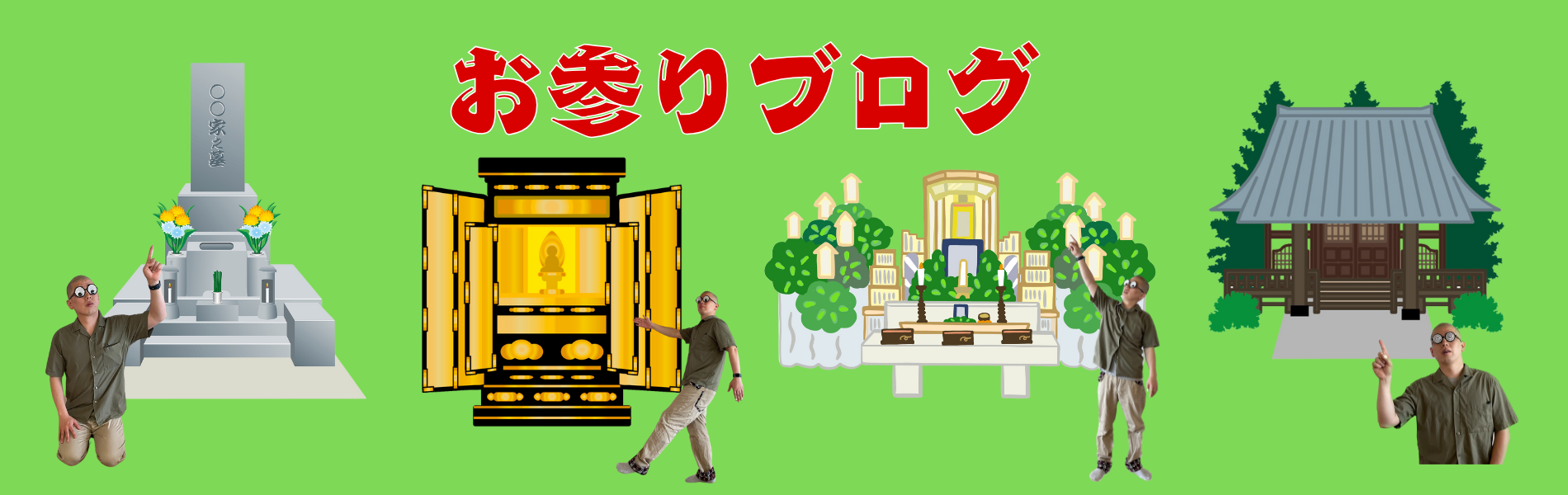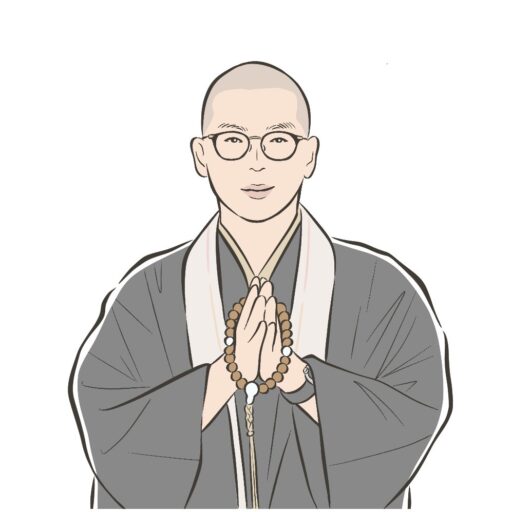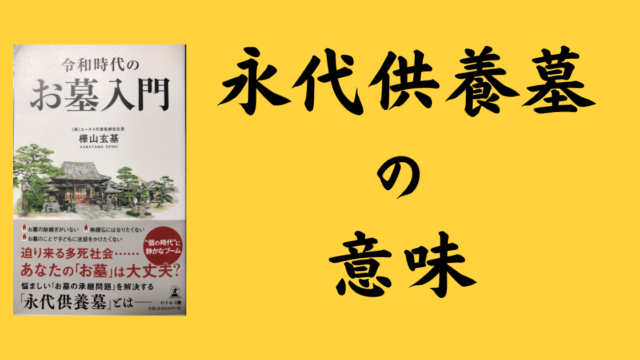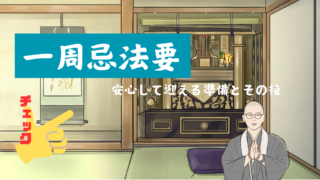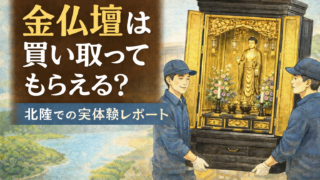喪主は誰がする?相談すれば心配せずとも大丈夫。

本記事では、家族構成や慣習、役割分担など、喪主を選ぶ際の基準と注意点を解説します。納得のいく喪主選びのための参考にされて下さい。
喪主とは? その役割と責任
喪主は、葬儀を主宰する遺族の代表者です。
葬儀社との打ち合わせや、参列者への対応、お礼など多岐にわたる内容の判断をしていきます。
- 家族や親族を代表する者
喪主は、その葬儀が「家として行うもの」であることを示す代表者です。家族間、親戚間の意見の取りまとめがうまくいかないこともあると思いますが、落ち着いて柔軟な対応をしていきましょう。参列者の方々への挨拶も大切な役割となります。 - 費用負担と会計管理
葬儀費用は遺産や香典でまかなう場合もありますが、どの程度負担するかは家族によって様々です。喪主が主体的に費用管理を行うケースも多く、親族間の認識を合わせる必要があります。この会計に関する仕事は、別で施主という役割で喪主とは別の方が担うこともあります。 - 葬儀後の手続きや法要の準備
葬儀後にも、死亡届の提出や相続の手続き、四十九日法要や納骨などのお寺さんとのやり取りも喪主が中心となって、それらを進めることが一般的です。
これらを踏まえて、「喪主」を決めていきましょう。
喪主を決めよう。一般的な選び方と背景

以下に一般的な選び方と、その背景をご紹介します。
1. 配偶者が喪主を務める
- 夫や妻が亡くなった場合
故人と最も近い関係にいる配偶者(妻や夫)が喪主を務めることが一般的です。家族を支えてきた中心的存在であることが多く、参列者からも自然な流れとして受け止められやすいでしょう。
ただし、高齢の配偶者が一人で喪主を務めるのが難しい場合は、子供や親族がサポートに回り、実質的に共同で喪主の役割を担うこともあります。
2. 長男や長女など、子が喪主を務める
- 長男が亡くなっている場合や一人娘の長女
これまでの慣習では、基本的に“長男が喪主”という考え方が主流でした。ただし家族事情によっては、長女が務めることもあります。経済的な負担や家族内での合意形成を考慮して、家族全体で話し合うことが大切です。長女が嫁いでいている場合は、その夫が娘婿として喪主を務めることが多いです。 - 同居している子供が務める
同居家族がいる場合、日頃から故人のケアを担っていた子供が喪主を務める例もあります。親族への連絡や実務を進めやすい環境にある点がメリットです。
3. 親や兄弟姉妹が喪主を務める
- 独身・子が未成年
配偶者や成人した子供がいない場合、親や兄弟姉妹が喪主を担うことがあります。家族形態によっては、祖父母が孫を見送る形になる場合もあるため、親族同士で負担を分担しながら進めましょう。 - 家庭環境や縁故関係による選択
故人との縁が深い血縁者が喪主を務めるケースもあります。特に、親族が遠方に住んでいて集まりにくい場合は、近くに住んでいる親や兄弟姉妹が引き受けることが多いようです。
喪主を選ぶ際に考慮すべきポイント
喪主を決めるにあたっては、経済的負担や時間的余裕、近隣や親族とのつながりなど、複数の側面を検討する必要があります。
1. 体力的・精神的負担
- 喪主は葬儀全体を取り仕切るため、精神的にも身体的にも大きな負担がかかりやすいです。
特に、肉親を失った喪失感が大きいタイミングで実務を行う必要があるため、サポート体制が整っているかどうかが重要です。負担でもありますが、大切な方のお身体があるうちの最後の御礼の時間でもあります
2. 家族や親族の合意
- トラブル防止のための事前の話し合い
葬儀は短期間で準備が進められるため、親族間の意思疎通不足による衝突が起きがちです。あらかじめ「誰が喪主を務めるか」を家族で話し合っておくことが、後々のトラブルを回避する鍵となります。終活のひとつと言えますね
3. 実際の手続きや参列者への対応
- 死亡届や役所への届け出
役所への死亡届や火葬許可証の手配など、書類関連の業務が多くあります。連絡先の把握や書類の管理など、事務的作業が得意な人がサポートするとスムーズです。 - 参列者へのあいさつとお礼
喪主は葬儀当日、弔問客への感謝を伝えたり、式進行を見守りながら関係者とやり取りするため、臨機応変な対応が求められます。自信がない場合は、配偶者や子供、親族などと役割を分担し、負担を軽減する方法を検討しましょう。
喪主を選ぶタイミングと注意点
葬儀の準備期間は非常に短く、時には突然やってきます。
配偶者や長男が務める場合には問題は起こりにくいですが、兄弟や親族が務める場合には、生前から話し合い、あらかじめ誰が喪主になるか決めておくと、いざという時に落ち着いて対応することができます。
今は遠方にいたり、関係が薄くなってきており、生前から親族間、兄弟間である程度話し合っておくことは決して簡単なことではありません。最後の感謝を伝える大切なものでありますが、経済的、時間的に労力のかかることなので、やはり故人のためにも葬儀のときに縁ある方々でのいさかいは避けたいものです。
1. 元気なうちに話し合う
- 意志の尊重と円滑な進行
元気なうちに葬儀の形や喪主の人選を話し合うことで、故人の希望や家族の考えを反映しやすくなります。特に親が高齢の場合は「どんな形で見送って欲しいか」を事前に聞いておくと、後悔のない葬儀につながります。何を決めれば良いのか分からないということがあれば、エンディングノートを参考にしてみても良いと思います。
2. 代理喪主・共同喪主という選択
- 高齢者や病気の家族に配慮
高齢の配偶者が形式上は喪主となり、実務面は子供が担当するといった「共同喪主」というという形をとることもあります。
皆が協力し合うことで、負担を分散できるメリットがあります。 - 遺族や親族の関係性を考慮
親族が多い場合や、親戚間のやり取りが活発でない場合などは、代理喪主を立てて会計管理や参列者の対応を分担する方法も検討するとよいでしょう。
実際に喪主を決めたあとの流れ
喪主が決まったら、以下のような流れで葬儀の準備や運営を進めていきます。
- 葬儀社の選定・打ち合わせ
喪主が主に葬儀社と連絡をとり、日程や費用、式の形式などを詰めます。 - 親族への連絡
親族や親戚へ葬儀日程を連絡すると同時に、必要な役割分担(受付など)をお願いすることがあります。 - 会場設営・祭壇準備
葬儀のスタイルによっては、会場の大きさや祭壇の設営に差があります。葬儀社がもちろん把握はしておりますので、宗派や宗教に合わせて準備を進めましょう。 - 通夜・葬儀・告別式
喪主は閉式時の挨拶をしたりと、参列の方々に御礼を伝えたり、遺族代表として挨拶をします。 - 香典返しや後日の挨拶回り
葬儀後は香典返しの手配や、各種手続き(保険、年金など)を行い、参列者や近隣の方々へのお礼の挨拶をします。
まとめ
喪主は葬儀の中心となる大切な役割です。
故人の遺言があり、喪主の指定も書かれているならば、その遺言に従います。
配偶者や長男・長女など、誰が務めるのかは各家庭によって異なりますが、基本的には
①配偶者
②長男
③次男以降の直系の男子
④長女
⑤次女以降の直系の女子
⑥故人の両親
⑦故人の兄弟
となっていきます。一人娘で家を出ている場合は、その夫。
故人が独身の方であればご両親やご兄弟、ご兄弟が入院や体調不良であればそのお子さんが喪主を務められたというケースもあります。家を出て嫁に入った、しかし配偶者が亡くなり子がいないという場合など、どちらの家の者が喪主や金銭の負担を担うかという問題が起こる可能性が高くなってきます。
そういった場合には、一人がすべてを担うという形にすべきではありません。問題が起こり、「あんな人だとは思わなかった」「ああいう人だと良く分かった」と葬儀を機に、縁を切ったというお話も聞いたことがあります。
生前から話し合いのチャンスをうかがっておきましょう!