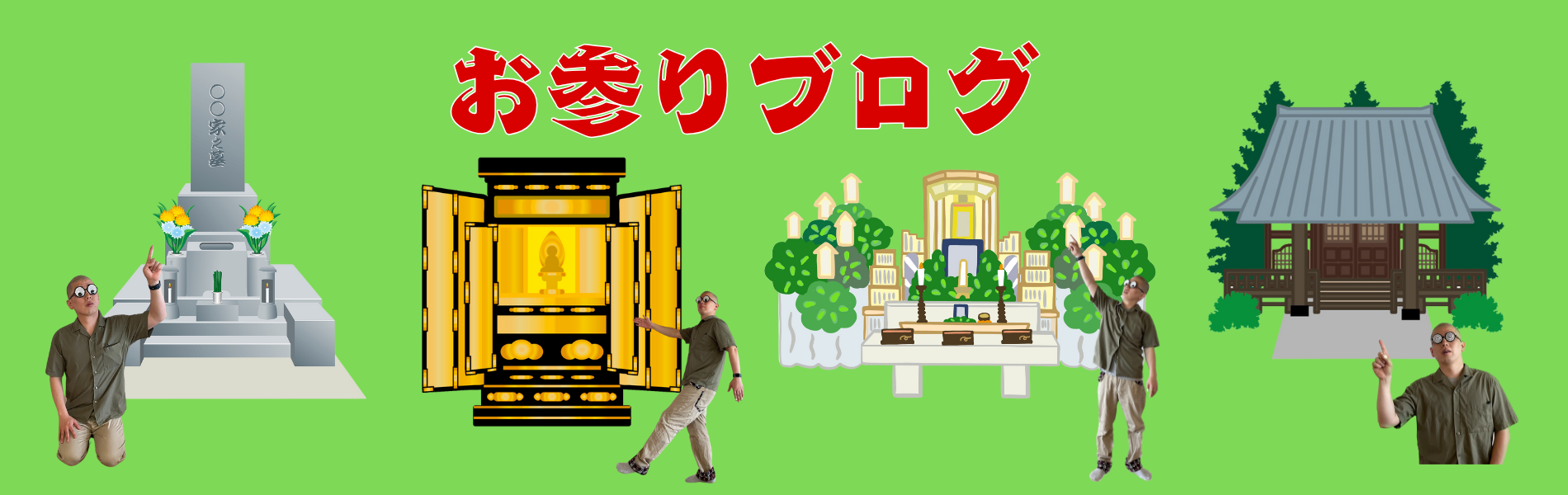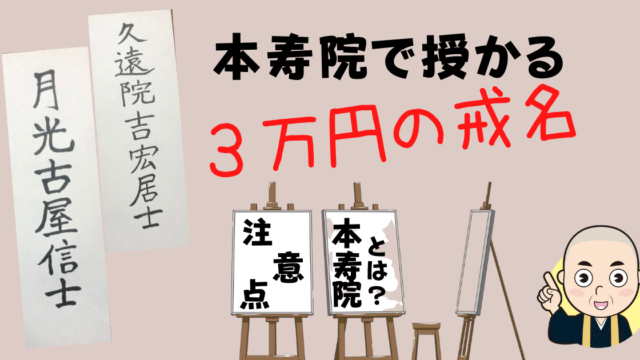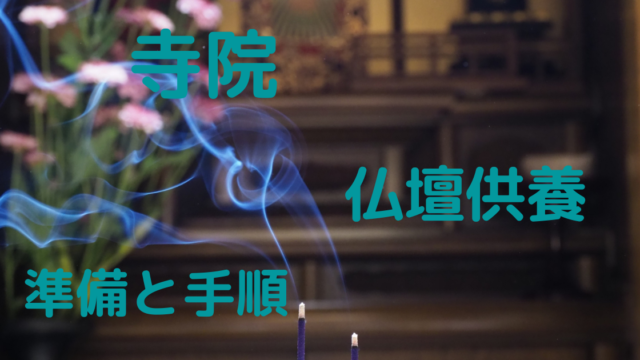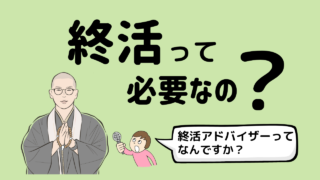お香典から考える。霊魂と仏様の違いはありますか?

お坊さんをしていると、友人にお香典の書き方について聞かれることがあります。
そこで書き方について調べようと思ったのですが、調べているうちに、なぜそう書くのか、今の時代の私たちは霊や仏様についてどう思っているのかが気になってきましたので、私たちにとって霊とは、仏さまとはというお話が中心になります。
石川県で浄土真宗の僧侶をしていると、「御仏前」が当然のように思っていました。ですが全国的に見ると「御霊前」が一般的のようです。
書き方ということになれば、仏教では「御霊前」と書かれることが多く、亡くなられた方の霊が、四十九日をもって仏様に成仏すると考える宗派が多いから四十九日では「御仏前」と書くとされています。
でも浄土真宗では、亡くなられた方はすぐに仏様になると考えられていますので、浄土真宗の葬儀では「御霊前」ではなく、「御仏前」と書きましょう。
お香典の書き方は以上で大丈夫です。
ただし地方によって違うのだと思います。石川県では、お通夜から「御香典」と書くことが多いですし、御霊前と書くことは少ないと思います。
よくお寺に来てくれる門徒さんに、「お坊さんの当たり前は、わしらの当たり前じゃないぞ」とよくお叱りをいただいておりますので、その言葉を心に留めて、もう一度考えてみたいです。
そもそもお香典って?

お香典は今は喪家の経済的な援助になりますが、お香典の名の通り元々は香りを故人にお供えするという意味ものでした。
仏教の考え方で故人は四十九日の成仏までの間、線香の香りを食事とされているという説からです。線香を絶やさないことが供養とされたのはここからでしょう。
儀式の中でも焼香という時間があります。
焼香には場を清めるという、浄土の香りを表す、全ての人にいきわたる仏の功徳を表すなどの意味がありますが、私たちも喪服を着るなど身を整えますが、儀式という場を整えるということです。
お葬式があってから四十九日法要までの間、中陰壇という故人を供養するためのものがあります。そこにはよく渦巻き状の線香がありますが、こういったことから10時間以上もつ線香も生まれたのでしょう。
友人と話をしてみたのですが、御霊前と御仏前という概念がありませんでした。
お香典はお香典で、それ以外あるんか?ということでしたね。
まだ、私の歳(35)だと、通夜葬儀以外、49日にお香典を持っていったことがない人が多いので、御仏前、御霊前にピンとこない人が多いのです。
いつか必ずお通夜や葬儀に行く機会はあります。それまでに一度考えてみましょう。
御霊前の意味
御香典に御霊前と書くのは、喪家の宗派に合わせるということで、葬儀のマナーの1つです。自分が死後の世界をどう思っているかを表すわけではありませんが、その意味を理解しておくのは大切なことです。
私たちは霊魂を存在するものとしてきました。死後の世界があり、そこに御先祖様の霊魂がある。その御先祖様の霊魂をお盆に御迎えしたり送ったり、存在を感じ繋がりを感じてきたのだと思います。

今はどうでしょうか?皆さんは霊や魂の存在をどう感じておられるでしょうか?
例えば、私は霊魂の存在は信じていないつもりです。浄土真宗の盛んな石川の地で育ったからだと思います。浄土真宗では霊魂という言葉は使いません。私を導いてくれる存在を仏様としていただくので、御先祖は私たちにとって仏様と考えます。
しかし、霊魂の存在を信じている方もおられます。門徒さんとお話をしていても、「母がその台所にきた」、「押入れの中から音がした」そう言われる方もおられます。聞く人が聞いたら幽霊とも感じられますが、その方は怖いという意味では言っていません。母が来たと、温かい雰囲気でお話をしておられました。
また私は経験していませんが、お寺の誰もいないはずの本堂で人の気配がする。行ってみると誰かが座っているんだけど近づいていくと姿が見えなくなった。
そのあと檀家さんから電話があって、おじいちゃんが亡くなったと言われて、そのお話をしたらお知らせに行ったんだろうというお話をしたと聞いたこともあります。
もちろん良い面だけではありません。成仏できない霊魂は生きている私たちに悪い影響を及ぼす、祟ると言われてきました。祟りをおこす霊魂の鎮魂としての意義も、儀式には求められていました。
そして私も今、信じていないと言いましたが、妻や子どもがもし亡くなって、その存在をすぐに仏さまとして感じられるかどうか。もう一度、幽霊でもいいからこちらの世界へきてほしいと願うかもしれません。
霊という概念が無いという方もおられると思います。
皆さんの周りでも亡くなった後は無になる。死んだら終わりという考えをもつ方が多いでしょうか?
しかし、戦争で亡くなられた方々を私たちは戦没者追弔の法要で供養するときには、霊として供養する。どのような考え方をもっていたとしても、その場では私たちはその場の雰囲気に従います。
一度死んだ方が死後はこういう世界だったと伝えてくれれば信じられるかもしれませんが、それは難しいでしょう。
書いていながら、私の中でもまとまっていません。どうしても霊魂と言うと、供養して成仏させるというイメージがありますが、浄土真宗ではその考えはしないので、その環境で育ってきた私は霊魂の存在を感じにくいのでしょう。
喪家の方々が死後についてどう思っているか、知っていればいいですが宗教のことは尋ねにくいことかもしれません。
御香典をもっていくときは、こうやって霊魂について理性的に話を出来るような場ではありません。普段は死んだら終わりと考えていても、故人は無に帰りましたねと言えるはずもありません。香典の書き方というよりも、喪家の方々を傷つけないように、そして亡き人がそこにいるかのような表現を今もしているのでしょう。
私が思う御霊前についてお話させていただきました。
御仏前

私たちは亡くなって仏様になる。
浄土真宗では仏さまになるまでに霊魂という期間はありませんが、仏壇やお墓、儀式を大切にすることは同じです。
霊魂と呼ぶか、仏と呼ぶか、目に見えないその存在を大切にするという意味に変わりはありません。
仏壇に「魂入れ」という儀式がありますが、浄土真宗でも魂という言葉を使わず、「御移徒」(ごいし)という名前で仏さまが仏壇に移動するという法要があります。
魂がこちらに返ってくるという表現はしませんが、「回向」(えこう)というこちらの世界へのはたらきを表す言葉も浄土真宗でよく使います。
こんなことを言えば怒られるのかもしれませんが、私たちが心に感じる存在の呼び名が違うだけだけだと思うこともあります。
本当にあるのかと問われると死後のことなので分からないことが多いことですが、そう思うことで救われてきた面は大きいです。大切な方と繋がっていられると思えることは死を必ず経験する私たちにとっては心強いことです。
多くの人々が仏教に親しんできたのは事実で、仏さまに悪い印象をもつ人はいない。その領域で仕事をする私のような僧侶への印象は良くも悪くもあるかもしれませんが。
仏教は、人々が苦しみから解放されるための手段として伝わっているし、その苦しみの最たるものである死へは深く仏さまが関わっているのは自然なことであると思う。
お墓に私も入るということは亡くなった方と再会するという気持ちになれる。精神的な再会は霊魂という言葉を使わない私たちでも大切なことだと思っています。
日本には至る所にあるコンビニよりも多くの寺院がありますし、昔に比べて行く機会は減ったと思いますが、仏さまと聞くと親しみを感じる人はたくさんいると思います。
亡くなっても、その親しみのまま仏さまとして亡き人を感じていたいという思いはあると思います。
仏教では昔、亡くなるときには仏様が迎えに来ると言われていました。
そのために、亡くなる直前まで周りで南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と申して浄土へ往生させるということをしたり、亡くなる方の五本の指に糸をつけて仏像の指と繋げて亡くなっていくという儀式があったりもしたと聞いたことがあります。
今よりも死後私たちはどうなるのかを気にしていた、そこに仏様の救いは不可欠だったのだと思います。
存在を証明できなくても、仏教徒の中で仏様は間違いなく存在してきました。霊魂も同じで、信じる人の中には間違いなく存在してきたものですし、有る無いを論じることが出来ないものなのだとあらためて思いました。
そしてマナーも大切ですが、霊魂や仏様についてどう感じているかを周りの方々とお話してみていただけたら嬉しいなと思いますし、コメントしていただけるとなお嬉しいです。